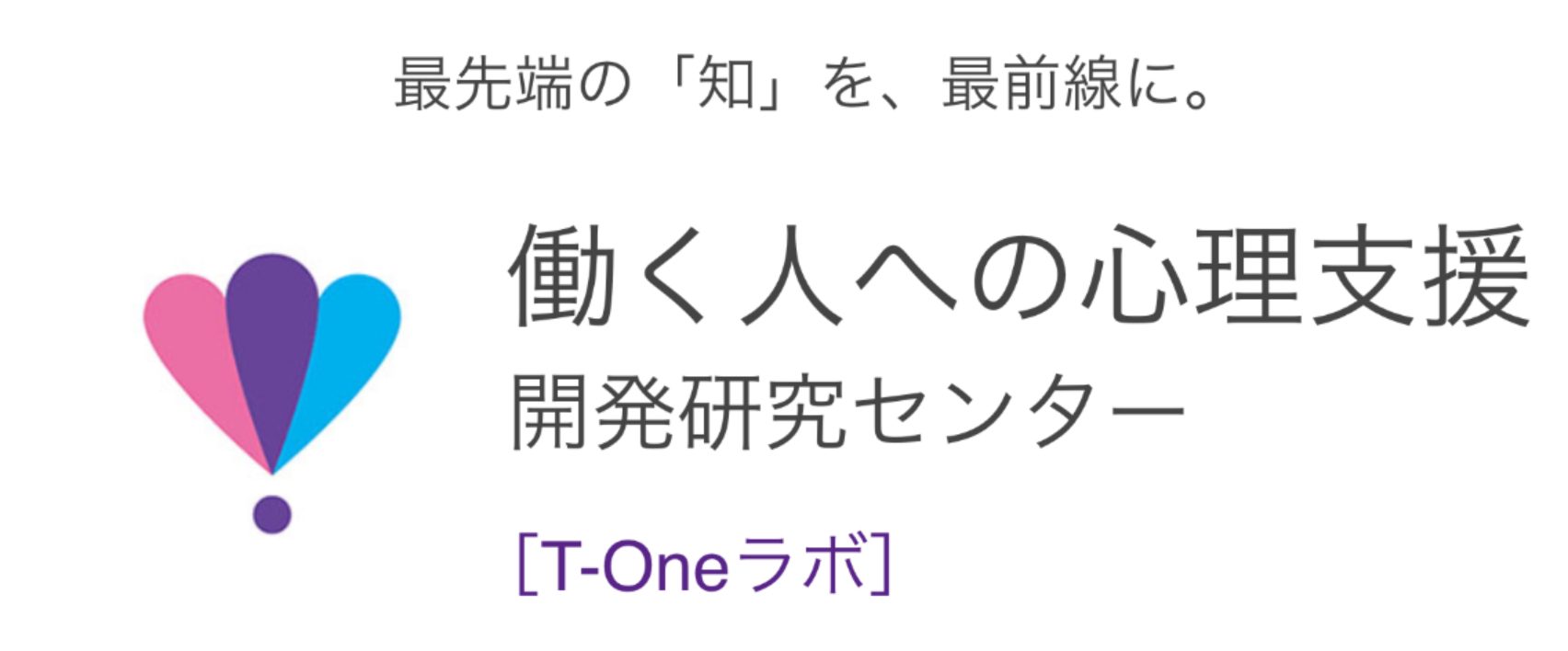自分を深く理解して初めて
他者を理解して支援できる
JCDAの国家資格キャリアコンサルタント更新講習に「ケース演習<働く人の心理学>」という技能講習があります。今回のゲストは、その講師を務める岡田昌毅先生。岡田先生は筑波大学でキャリア発達やキャリア・カウンセリング、人材育成などに関連する研究活動に長年取り組んでいます。その視点や考え方はきっと皆さんの参考になるものと思われます。

筑波大学 人間系 特任教授
働く人への心理支援開発研究センター長
岡田 昌毅さん

日本キャリア開発協会(JCDA)
理事長
大原 良夫
電気工学のエンジニアから キャリアカウンセリング領域へ
先生がキャリアに興味を持たれた経緯からお聞かせください。
 司会:JCDA事務局長 佐々木 好
司会:JCDA事務局長 佐々木 好岡田 私は電気工学科出身で、エンジニアとして新日本製鐵(現日本製鉄)に入社しました。ただ、入社して3~4年が経つと、「自分はエンジニアに向かない」と考えるようになりました。
大原 なぜそうお感じになられたのですか。
岡田 機械や図面を相手にしたり、設計したりすることが、根本的に合わなかったのです。安易に就職したので、働いて初めて現実と向き合うことになりました。
大原 そうなのですね。
岡田 ひたすら悩む毎日を送っていましたが、入社6年目に社内公募があることを知りました。早速、「人に関わる仕事がしたい」と応募して、教育ビジネスを手掛けている子会社に出向しました。
大原 教育ビジネスですか。
岡田 4年間出向していたのですが、会社を清算することになり、再度出向することになりました。出向先は新日本製鐵とグループ企業の人材育成を担う会社で、人材育成の基礎を学びました。ただ、そこにも1年4ヵ月間在籍しただけで、新日本製鐵本体の新規事業部門に異動となり、「職種転換教育の企画・実行」を担当することになりました。
大原 社員の職種を変えるように、ということですか。
岡田 若手を中心とするエレクトロニクスのエンジニアに対して、ITエンジニアに移行するよう教育する役割でした。20人1組につき3ヵ月間の教育プログラムを計6回、約120人を対象に1年半にわたって実施しました。でも、そのうち3割くらいの人はスムーズに移行することができません。そうした人に私ができたことは、一緒にお酒を飲んで愚痴を聴いてあげることくらいでした。
大原 難しい立場ですね。
岡田 「人に関わる仕事がしたい」と言って異動したのに、「自分は何もできない、何の力もない」という現実に直面しました。そこで「何か学ばなければいけない」と思って探している中で行き着いたのがカウンセリングでした。たまたま見つけた「社会人のための大学院フェア」に、筑波大学のカウンセリングコースが出展していたのです。心理学の基礎知識がなかったので予備校に通い、2回目の受験で入学できました。
大原 何歳くらいの頃ですか。
岡田 39歳でした。
大原 仕事がお忙しい中、夜間の大学院に通ったのですね。
岡田 そうです。そしてカウンセリングコースが修了する頃、厚生労働省が標準レベルのキャリア・コンサルタントの民間資格をスタートしましたので、私も受講・受験しました。そのような流れでキャリアカウンセリングの領域に入ってきました。
大原 人材育成とキャリアカウンセリングとでは、先生にとってどちらが柱になっているのでしょうか。
岡田 「自分のアイデンティティは何か」と振り返ると、人材育成だと思います。人の成長や発達をお手伝いしながら見守っていくことが、私が最もやりたいことなんだろうと思います。なかでも企業領域の「人の成長・発達・学び」が得意分野だと思います。
カウンセリングの社会人大学院と 働く人への心理支援開発研究センター
先生は2006年に筑波大学の教員になられていますが、改めて現在のご活動をお聞かせください。
岡田 2006年からずっと取り組んできたのは、東京キャンパスでの社会人大学院です。修士課程も博士課程も担当してきました。
正式には「カウンセリング学位プログラム(博士前期課程)」「カウンセリング科学学位プログラム(博士後期課程)」と呼ばれます。
前者の修士課程の特色は二つあります。一つは、カウンセリングを心理療法や治療的カウンセリングに限定せず、広い範囲にわたる援助活動としていることです。もう一つは、リカレント教育の視点からカウンセリング学習を捉えていることです。
基礎研究というよりも、現実場面での問題解決という実践的なアプローチに重きを置き、研究能力と高度の専門性を備えた専門的職業人の育成と再教育を志向しています。
大原 大学院生の方は何名くらいいらっしゃるのですか。
岡田 修士課程の定員は1学年23人、2学年合計で46人です。博士課程は1学年4~5人で、3学年合計十数人です。
大原 何か苦労なさっていることはございますか。
岡田 大学院生の多くは心理学を専門に学んできたわけではありませんが、皆さんに共通するのは、職業経験の中で「人」に興味を抱き、
何らかの現象や事象に対して「解決したい」「明らかにしたい」などの課題感を持って取り組んでいることです。それに対して私は、「皆さんがやりたいことをどうすれば研究として
形にできるか、一緒に考えていきましょう」というスタンスです。ですから、苦労とは感じていません。
大原 そうなのですね。
岡田 むしろ、私が得ているもののほうが大きいかもしれません。私が企業の現場を離れて恐れているのは、
現場のことがわからなくなってしまうことです。でも、社会人大学院生と一緒に研究をしていると、現場で起きている最新状況を知ることができます。 もっとも、大学院生はたいへんだと思います。
仕事で時間が拘束される中で研究しなければいけませんし、レポートや発表もあります。ライフイベントもあります。でも、仲間と切磋琢磨し、励まし合いながら乗り越えていますので、非常に大きな成長につながっていると思われます。
大原 先生は「働く人への心理支援開発研究センター」のセンター長でもありますね。
岡田 はい、同センターはもう一つの活動の中心となります。
働く人への心理支援に関する研究を推進し、その成果を社会に還元することを目的として、2019年に設立しました。社会人大学院での実績に基づいた知見を基盤としながら、働く人や働く人を支える家族・組織のために、「人は、いつでも、いつまでも発達できる」という理念のもと、活動しています。
キャリコンの最大の課題は 「どのように質を高めるか」
少し視点を変えて、キャリアコンサルティングの未来について意見を交わしたいと思います。
大原 キャリアコンサルティングやキャリアコンサルタント(以下「キャリコン」という)の課題についてどうお考えですか。
岡田 「どのように質を高めるか」に尽きると思います。ただ、国家資格化されて法律にも関わりますので、難しい問題です。
大原 以前は「仕事で必要なので」という動機で資格取得をめざす人が多くいましたが、今は「とりあえず取っておこう」という人が増えたようにも思います。
岡田 そうかもしれませんね。それでも、質を高めるための施策は続ける必要があります。筑波大学としても、質を高めるためにどうすればいいかと考えて実施したのが「キャリア・プロフェッショナル養成講座」です。
大原 知らない読者もいるかと思いますので、改めてご説明していただけますか。
岡田 同講座は「働く人への心理支援開発研究センター」の活動の一環として行っているもので、企業・学校・行政機関など多様なキャリア支援領域における指導者レベルの人材の養成・強化を目的としています。全24日のプログラムで、国家資格キャリアコンサルタントまたはキャリアコンサルティング技能士の有資格者を対象とした、いわば大学院レベルのカリキュラムです。ここで学んだ方々がビギナーや成長過程の方を指導できるよう養成することが、筑波大学の役割だろうと考えました。

キャリコンのめざすべき姿は
組織へのアプローチもできる人
大原 現在、キャリコンの有資格者は約8万人で、今後も増えていくでしょうから、指導者のレベルを高めることは重要ですね。
岡田 すでに第13期まで終え、修了生は約400人に上ります。その人数がさらに増え、成長した修了生同士で切磋琢磨して「誰かを育成・指導する立場にならなければ」と意識し行動してもらえればと思っています。組織へのアプローチも意識したカリキュラムですから、たとえば組織内の施策の立案・実施・検証などを含め、個人と組織の両方にアプローチできる指導者の養成をめざしています。
大原 キャリコンの質向上のためにはスーパーバイジングも重要ですが、制度として強制化するのは難しい面もあります。自分の意思で自由に指導者レベルをめざすことは大切なことだと思います。
岡田 「キャリア・プロフェッショナル養成講座」の定員は30名ですが、そこに集まる人は皆さん、指導者になることを意識しています。そうした場では人脈も形成されますので、その刺激によってさらに学びを深めてもらえればと思います。
「個人と組織の両方にアプローチできるように」とのことですが、当協会の会員からは「難しい」という声が多く聞かれます。
岡田 民間企業は営利を目的とした団体で、営利活動によって社会に貢献しています。そうであるならば、キャリコンは個に焦点を絞って、その人が幸せであることに向けて支援をすべきでしょう。
他方で、個々の人たちが元気にやりがいを持って生き生きと働ける場をつくる必要もあります。そうした場をつくるためには、どうしても組織にアプローチする必要がありますし、経営層が後押ししてくれるような仕組みや理念を浸透させていく必要があります。
これら両方を進めることによって個が幸せになっていく構造なのですから、「私は組織へのアプローチはできない」という姿勢はいかがなものでしょうか。複数人で役割分担をして連携することも考えられますが、キャリコンのめざすべき姿は、組織へのアプローチもできる人だと思います。企業内でキャリア支援を定着させるためには、そうした人材をより多く輩出して、結果的に経営にも資するようにつなげていく必要があります。

スーパーバイジングも重要だが
強制化するのは難しい面も
大原 「キャリコンは個人の支援をするのが仕事で、組織へのアプローチは人事部門の仕事」と思っている人もいるようです。
岡田 人事担当者が個のキャリア支援を明確に意識して考えていればそれでもいいでしょうが、人事の立場・役割で考えている担当者は、おそらく個のことを細かく見ることはできないと思います。私が民間企業で働いている時は、個への支援の実現をめざし、経営層に予算を認めてもらうために、経営側の視点で物事を考えた上で施策を提案しました。また、経営層だけではなく、人事部門に対してもアプローチをすることが大事だと思います。
自己理解は成長プロセスの根本 意識して繰り返し考えよう
今後に向けて、ほかに気になっていることはございますか。
岡田 キャリコンにとって、たとえば「就職したい」などの相談者のニーズに応えて適切な支援をすることは重要かつ必要です。ただ、それに留まらず、相談者がその後の人生をどう歩んでいけるかを考える時間を増やす必要があると思います。「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」という言葉もあるように、相談者が自分で自らのキャリアを切り拓いていけるように促進する支援が必要だと思うのです。そのためには、キャリコン自身がしっかりと自己理解をすべきです。
大原 なるほど。
岡田 誰にも自分の負の側面があり、過去の葛藤の経験などによって成長してきたはずです。そうしたことを含めてじっくりと自分に向き合い、自分をとことん理解しようと深めていくことによって初めて他者の理解が深まるのだろうと思います。
大原 キャリコンとしての専門性を高める以前の問題として、「どのように専門性をつくっていくのか」という段階で自己理解が必要な気がします。
岡田 自己成長のプロセスには、自分のものの見方や考え方の蓄積がありますが、その根本にあるのはおそらく自己理解です。自分を理解していない人が他者を簡単に理解できるとは思えません。もっとも、自己理解は非常に難しいことです。一生理解できないかもしれません。だからこそ、意識して考えることを繰り返し続けることが大切です。
大原 私たちも成長を促す役割には非常にこだわっています。相談に来る人は「すぐに解決してもらう」ことをイメージしがちで、たとえば「とにかく早く仕事を紹介してほしい」という人もいます。でも本来は、相談者の将来のウェルビーイングを担えるようなキャリコンが必要なのだろうと思います。
岡田 そうですね。ニーズに応える方法論としてテクニカルなスキルも絶対に必要ですが、それは本質的な部分、つまりものの見方や考え方、自分に対する真摯な態度があって初めて意味を持つように思います。本質的な部分は相談者への態度にも反映されます。
越境学習で新たな社会を学び 広い視野で知見を持ってほしい
先生が筑波大学に入られた頃と今とでは、キャリア形成の流れに変化は生じていますか。
岡田 最近、「キャリア自律」という言葉がよく聞かれます。「自分のキャリアは自分で考えて主体的に形成しましょう」という考え方自体は望ましいと思いますが、「キャリア自律をした後は何をめざすのか?」が気になります。「キャリア自律が行われた後に描かれている望ましい姿は何なのか」を考える必要があるように思います。
大原 キャリア自律にも関係しますが、当協会が考えていることについてシェアさせていただきます。私たちには「キャリアカウンセリング機能を社会システムとして具現化する」というビジョンがありますが、キャリアのことを意識していない人に「キャリアカウンセリングを受けませんか」と誘っても難しい面があります。そこで、すごろくゲームのツールを使って自分の人生に興味を持ってもらうなどの工夫をしています。そうした中で、特に企業で活躍する会員には「越境学習」をしてほしいと思っています。それによって、企業内の価値観だけでなく、社会で起こっていることに触れて学び、自社に持ち帰ってくるような仕組みをつくりたいと思っているのです。
先日、APCDA(アジア太平洋キャリア開発協会)の会長も「我々には地球人としての役割もある」という旨を発言していました。特に企業の人材育成担当者には、そうした公共性や市民性も大切ではないかと思っています。
岡田 越境学習という意味では、まさに社会人大学院が典型例です。多種多様な23人が集まり、単なる学びだけでなく、現場で起きていることを研究に落とし込んでいますので、「自分にはこんなに知らないことがあったんだ」と痛感した上で、相互に複雑に学び合っています。その学び合いと切磋琢磨によって、「自分は人間として何をすべきか」を広い視野で考えるように成長しているように感じられます。知識レベルを超えた越境学習のようなものが進んでいます。
大原 先生の文脈とは少し違うでしょうが、越境学習的な場をいろいろつくり、「人はさまざまな役割を持ち、さまざまな場で活躍している」ということを、CDA会員の人には意識してほしいと思っています。そして、さまざまな役割をどう調整していくかの考え方を、CDAは相談者に示して支援できるようになってもらえればと思います。
岡田 キャリアコンサルタントは本来、広い視野で知見を持つことが求められますね。
自分の役割を単純化するのではなく、自己理解を深めると同時に、自分の役割も棚卸することで成長するように思います。
岡田 役割は変化していくでしょうから、自己理解と同様、自分の役割の理解も続けていくべきだと思います。
大原 自分一人で考えるよりも、人との交流で活性化するのかもしれませんね。
岡田 表層的な交流ではなく、葛藤するような場面を経験する必要があるように思います。社会人大学院の例で言えば、「起きていることの本質は何だろうか?」と考え抜くことも一つの形です。
最後に、JCDAに対するご意見やご要望がございましたら、お聞かせください。
岡田 今、JCDAさんと最も関わっているのは、キャリアコンサルタント更新講習の技能講習「ケース演習<働く人の心理学>」の講師役です。講習で強く意識しているのは、1人でも多くの方が何かに気づき、「次の学びにつなげよう」と思ってくださることです。「自分はもっとこういうことを深めていかなければいけない」「こういうことを学んでいかなければいけない」「今後こうしていかなければいけない」などと気づいてもらえる講座を心がけています。ほかの講座も含め、そうした工夫を引き続き行うことによって、皆さんが一歩ずつ成長していくことにつながるかと思います。
大原 本日は貴重なお話をありがとうございました。
(取材:2025年3月13日)
★JCDAの国家資格キャリアコンサルタント更新講習についてはこちら↓
https://www.j-cda.jp/seminar_cat/consultant